この記事では、定番の鬼ごっこから少し変わった鬼ごっこまで、様々な種類のルールや遊び方を詳しく解説します。年齢別のおすすめや場所別の選び方、遊び方のアレンジ方法などもご紹介するので、子供から大人まで、みんなで鬼ごっこを楽しめます!安全に遊ぶためのポイントも忘れずにチェックしてくださいね。
王様鬼から氷鬼まで!定番鬼ごっこルール解説
このセクションでは、誰もが一度は遊んだことがある定番の鬼ごっこ、「王様鬼」「氷鬼」「色鬼」のルールを改めて確認し、遊び方のポイントやバリエーションもご紹介します。基本的なルールを理解することで、より戦略的に、そして楽しく鬼ごっこをプレイできます。
王様鬼
王様鬼は、鬼が捕まえた人を自分の仲間(家来)にして、一緒に他のプレイヤーを捕まえる鬼ごっこです。鬼ごっこの中でも特にチームワークが重要になります。まず、鬼を一人決めます。鬼は「王様だーれだ!」と叫びながら他のプレイヤーを追いかけます。鬼にタッチされたプレイヤーは鬼の家来になり、手をつないで一緒に他のプレイヤーを追いかけます。全員が鬼の家来になったらゲーム終了です。
たとえば、公園で10人で遊ぶ場合、最初に鬼を一人決めます。鬼は「王様だーれだ!」と叫びながら走り回り、タッチされた人は鬼の家来になります。家来が増えるごとに、繋がった手の列は長くなり、捕まえる範囲も広がっていきます。全員が家来になったら、最初に鬼になった人が勝ちとなります。
王様鬼は、家来が増えるにつれて鬼の勢力が拡大していくのが特徴です。逃げているプレイヤーは、鬼の列の動きを読むことが重要になります。また、鬼になったプレイヤーは、どのように家来と連携してプレイヤーを囲んでいくかが勝利のカギとなります。
氷鬼
氷鬼は、鬼にタッチされるとその場で動けなくなる(凍る)鬼ごっこです。他のプレイヤーにタッチしてもらうことで凍った状態が解除されます。鬼以外全員が凍ってしまったら鬼の勝ちです。
具体的には、まず鬼を一人決めます。鬼にタッチされた人は、その場で動けなくなり「氷」の状態になります。凍った人は、他のプレイヤーにタッチしてもらうことで復活できます。全員が凍ってしまったら鬼の勝ちで、次の鬼を決めてゲームを続けます。
氷鬼は、凍った仲間を助けに行くか、それとも鬼から逃げるかの判断が重要になります。助けに行くことで自分も凍ってしまうリスクがありますが、仲間を多く残すことで鬼を倒せる可能性も高まります。状況判断と仲間との協力が鍵となる鬼ごっこです。
色鬼
色鬼は、鬼が指定した色のものに触れているプレイヤーが安全というルールです。鬼は「赤!」のように色を指定し、その色のものに触れていないプレイヤーを追いかけます。指定された色のものに触れていれば、鬼にタッチされてもセーフです。
たとえば、鬼が「青!」と叫んだら、プレイヤーは周りの青いもの、例えば青い服の人、青い遊具、青い車など、何でもいいので触れなければなりません。触れていないプレイヤーは鬼にタッチされてアウトになります。
色鬼は、周りの状況を素早く把握し、指定された色のものを見つける判断力が求められます。また、鬼になった人は、なるべく少ない人が触れられるような色を指定するのがポイントです。
ちょっと変わった鬼ごっこで楽しもう!
定番の鬼ごっこに飽きてきたら、少し変わったルールで遊んでみましょう!ここでは、「影鬼」「手つなぎ鬼」「ケイドロ」といった、少し変わった鬼ごっこをご紹介します。これらの鬼ごっこは、通常の鬼ごっことは異なる戦略や楽しさを提供してくれます。
影鬼
影鬼は、鬼がプレイヤーの影を踏むことで捕まえる鬼ごっこです。太陽が出ている日中にしか遊べませんが、普通の鬼ごっことは違った面白さがあります。鬼はプレイヤーの体ではなく、影を踏むことで捕まえることができます。プレイヤーは、自分の影を鬼に踏まれないように、建物の陰に入ったり、他のプレイヤーの影に隠れたりしながら逃げます。
たとえば、晴れた日の公園で遊ぶ場合、鬼はプレイヤーの影を踏むことに集中します。プレイヤーは、自分の影の位置を常に意識しながら、鬼の動きを予測して逃げなければなりません。木陰や建物の影などを利用して、戦略的に逃げるのがポイントです。
影鬼は、太陽の位置や周りの環境を把握する能力が重要になります。時間帯によって影の長さや方向が変わるため、常に状況を判断しながら動く必要があります。また、他のプレイヤーの影を利用するなど、工夫次第で様々な戦略が生まれます。
手つなぎ鬼
手つなぎ鬼は、鬼が捕まえた人と手をつなぎ、一緒に他のプレイヤーを捕まえる鬼ごっこです。王様鬼と似ていますが、手をつないだ二人が同時にタッチしなければ捕まえられないところが異なります。鬼に捕まった人は、鬼と手をつなぎ、二人で協力して他のプレイヤーを追いかけます。捕まった人が増えるたびに鬼の列は長くなり、捕まえる範囲も広がっていきます。
たとえば、5人で遊ぶ場合、最初に鬼を一人決めます。鬼が一人捕まえるごとに、手をつないだ鬼の列は長くなっていきます。最終的に全員が手をつないだらゲーム終了です。
手つなぎ鬼は、鬼同士の連携プレーが重要になります。どのように協力してプレイヤーを囲んでいくか、戦略を立てながら動く必要があります。また、逃げているプレイヤーは、鬼の列の動きを予測し、隙をついて逃げることが重要です。
ケイドロ
ケイドロは、「警察と泥棒」の略で、警察チームと泥棒チームに分かれて遊ぶ鬼ごっこです。泥棒チームは逃げ回り、警察チームは泥棒を捕まえて牢屋に入れます。制限時間内に何人の泥棒を捕まえられるかを競います。
具体的には、まず警察チームと泥棒チームに分かれます。泥棒チームは、警察チームから逃げながら、決められたエリア内を自由に動き回ります。警察チームは、泥棒を捕まえ、決められた場所に作った「牢屋」に入れます。制限時間になったらゲーム終了で、捕まった泥棒の人数を数えます。
ケイドロは、チームワークと戦略が重要になります。警察チームは、どのように協力して泥棒を捕まえるか、泥棒チームは、どのように逃げるか、それぞれ作戦を立てて動く必要があります。逃げるスリルと捕まえる達成感の両方が味わえる鬼ごっこです。
年齢別おすすめ鬼ごっこ
鬼ごっこは、年齢に合わせてルールや遊び方を変えることで、より安全に、そして楽しく遊ぶことができます。ここでは、2~3歳児、4~5歳児、小学生と、年齢別に最適な鬼ごっこの種類をご紹介します。それぞれの発達段階に合わせた鬼ごっこを選ぶことで、子供たちの成長をサポートすることもできます。
2~3歳児向け:簡単で安全な鬼ごっこ
2~3歳児は、まだ複雑なルールを理解することが難しいので、簡単なルールで楽しめる鬼ごっこがおすすめです。安全面にも配慮し、広い場所で、急に走り出したり止まったりしないように注意しながら遊びましょう。
- おすすめ鬼ごっこ:「だるまさんがころんだ」「むっくりくまさん」など、ルールがシンプルで、あまり走らない鬼ごっこがおすすめです。
- **遊び方のポイント:**鬼ごっこを通して、周りの状況を認識する力や、指示に従う力を養うことができます。遊びの中で、社会性や協調性を育むことができるようにサポートしましょう。
たとえば、「だるまさんがころんだ」では、鬼が後ろを向いている間に少しずつ近づき、鬼が振り向いた瞬間に動かないようにします。この遊びを通して、集中力や瞬発力を養うことができます。また、「むっくりくまさん」では、歌に合わせて体を動かし、リズム感を養うことができます。
4~5歳児向け:少しだけ複雑なルールに挑戦!
4~5歳児になると、少し複雑なルールも理解できるようになってきます。走るのが好きになる時期でもあるので、広い場所で思いっきり走れる鬼ごっこを取り入れてみましょう。
- おすすめ鬼ごっこ:「色鬼」「氷鬼」など、少しだけ頭を使う鬼ごっこに挑戦してみましょう。色鬼では、色の名前を覚えることにも繋がります。氷鬼では、助け合うことの大切さを学ぶことができます。
- **遊び方のポイント:**ルールを理解し、それに従って遊ぶことを意識させましょう。また、勝敗にこだわりすぎず、みんなで楽しむことを大切にするように促しましょう。
たとえば、色鬼では、鬼が指定した色のものに触れることで、鬼から逃れることができます。この遊びを通して、色の認識力や判断力を養うことができます。また、氷鬼では、凍った仲間を助けるために、他のプレイヤーと協力する必要があります。
小学生向け:チームプレーで盛り上がろう!
小学生になると、複雑なルールも理解できるようになり、チームワークで遊ぶこともできるようになります。戦略性が必要な鬼ごっこや、チームに分かれて競う鬼ごっこに挑戦してみましょう。
- おすすめ鬼ごっこ:「ケイドロ」「手つなぎ鬼」「王様鬼」など、チームで協力したり、戦略を立てたりする鬼ごっこがおすすめです。
- **遊び方のポイント:**チーム内で役割分担をしたり、作戦を立てたりすることで、協調性やリーダーシップを育むことができます。
たとえば、ケイドロでは、警察チームと泥棒チームに分かれて、制限時間内に何人の泥棒を捕まえられるかを競います。この遊びを通して、チームワークや戦略性を養うことができます。また、手つなぎ鬼や王様鬼では、捕まえた人と手をつないで、協力して他のプレイヤーを追いかけます。
場所に合わせた鬼ごっこを選ぼう!
鬼ごっこは、遊ぶ場所によって適した種類が異なります。屋内と屋外、それぞれの環境に合った鬼ごっこを選ぶことで、より安全に、そして楽しく遊ぶことができます。ここでは、室内と屋外それぞれにおすすめの鬼ごっこをご紹介します。場所の特徴を活かした鬼ごっこで、さらに盛り上がりましょう!
室内鬼ごっこ:雨の日でも大丈夫!
雨の日や暑い日など、屋外で遊べない時は、室内で楽しめる鬼ごっこがおすすめです。室内では、狭い空間でも安全に遊べるように、ルールを工夫したり、動きを制限したりすることが大切です。
- おすすめ鬼ごっこ:「だるまさんがころんだ」「宝探し鬼ごっこ」「こおりおに」など、あまり激しい動きを伴わない鬼ごっこがおすすめです。
- **遊び方のポイント:**家具や壁にぶつからないように注意し、安全に配慮しながら遊びましょう。また、周りの人に迷惑をかけないように、静かに遊ぶことを心がけましょう。
たとえば、「宝探し鬼ごっこ」では、鬼が隠した宝物を探し、見つけた人が次の鬼になります。この遊びは、探究心や観察力を養うのに役立ちます。また、「こおりおに」は、鬼にタッチされた人は凍ってしまい、他のプレイヤーにタッチしてもらうことで復活できるというルールです。狭い場所でも楽しめる定番の鬼ごっこです。
屋外鬼ごっこ:広い場所で思いっきり走ろう!
晴れた日には、広い屋外で思いっきり走れる鬼ごっこがおすすめです。公園やグラウンドなど、自由に動き回れる場所で、様々な種類の鬼ごっこを楽しんでみましょう。
- おすすめ鬼ごっこ:「ケイドロ」「逃走中(鬼ごっこの一種)」「王様鬼」「氷鬼」「色鬼」など、様々な種類の鬼ごっこが楽しめます。
- **遊び方のポイント:**周りの環境に注意し、車や自転車などに気をつけながら安全に遊びましょう。また、熱中症対策として、こまめな水分補給を忘れずに行いましょう。
たとえば、「逃走中」は、テレビ番組でもおなじみの鬼ごっこで、ハンターから逃げるスリルを味わえます。広い公園やグラウンドで遊ぶのがおすすめです。また、「王様鬼」や「氷鬼」は、大人数で遊ぶのに最適な鬼ごっこです。
鬼ごっこをもっと楽しく!遊び方のアレンジとバリエーション
定番の鬼ごっこも、少しルールを変えるだけで、全く新しい遊びとして楽しめます。ここでは、鬼ごっこをさらに楽しくするためのアレンジ方法やバリエーションをご紹介します。いつもの鬼ごっこに飽きてきたら、ぜひ試してみてください!
- **制限時間を設ける:**制限時間を設けることで、よりスリル満点の鬼ごっこになります。たとえば、5分間で何人捕まえられるかを競うなど、時間制限を設けることで、ゲームに緊張感と競争意識が加わります。
- **特殊なルールを追加する:**たとえば、「鬼は後ろ向きでしか歩けない」「鬼は片足でしか跳べない」など、特殊なルールを追加することで、難易度を調整したり、笑いを誘ったりすることができます。
- **道具を使う:**ボールや縄跳び、フラフープなど、身近な道具を使うことで、鬼ごっこのバリエーションを広げることができます。たとえば、ボールを鬼に見立てて、ボールに当たったらアウトというルールにしたり、縄跳びを使って陣地を作るなど、工夫次第で様々な遊び方ができます。
- **ステージを作る:**段ボールや毛布などを使って、簡単な障害物や隠れ場所を作ると、より戦略的な鬼ごっこを楽しむことができます。
これらのアレンジやバリエーションを参考に、オリジナルの鬼ごっこルールを考えてみるのも楽しいでしょう。子供たちの創造力を刺激し、遊びの幅を広げるきっかけにもなります。
安全に鬼ごっこを楽しむためのポイント
どんな遊びにも言えることですが、安全に楽しむことが何よりも大切です。鬼ごっこで夢中になるあまり、怪我をしてしまっては元も子もありません。ここでは、鬼ごっこを安全に楽しむためのポイントをご紹介します。
- **遊ぶ場所の安全確認:**鬼ごっこをする前に、必ず遊ぶ場所の安全を確認しましょう。危険な場所や障害物がないか、車や自転車が通る場所ではないかなどをチェックすることが重要です。
- **ルール説明と確認:**鬼ごっこのルールを始める前に、参加者全員にしっかりと説明し、理解しているか確認しましょう。特に、年齢の低い子供には、分かりやすく丁寧に説明することが大切です。
- **水分補給:**特に暑い時期は、こまめな水分補給を忘れずに行いましょう。脱水症状を防ぎ、安全に遊ぶために、水分補給は欠かせません。
- **服装:**動きやすい服装で遊びましょう。また、サンダルやヒールなどは避け、運動靴を履くようにしましょう。
- **休憩:**長時間遊び続けるのは避け、適度に休憩を取りましょう。疲れている時は、無理せず休憩することが大切です。
- **周りの人に配慮:**公園や公共の場で遊ぶ場合は、周りの人に配慮し、迷惑をかけないように注意しましょう。大声を出したり、危険な行為は避け、マナーを守って遊びましょう。
これらのポイントをしっかり守って、安全で楽しい鬼ごっこを楽しみましょう!
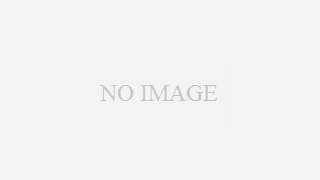



コメント